
節税保険ついに見直しへ
金融庁が是正勧告
「合理性を欠く。適切な対応を」
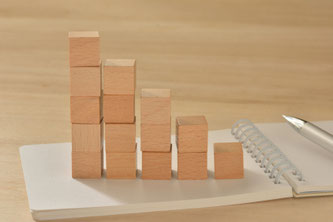
生保業界に対して複数回のヒアリング調査を繰り返てきた金融庁が、ついに「節税保険」の規制に乗り出した。11月中旬に開かれた業界との意見交換会で、10数社に対して一部商品の設計について是正を要求した。支払った保険料の全額が会社の損金となり、ほぼ全額が解約返戻金として戻ってくる貯蓄型保険は中小企業の社長にとって強い味方だったが、今後はそうした保険の旨味がなくなってしまう恐れも否定できない。社長さんが取るべき〝保険戦略〞はどのようなものか、業界の流れから読み解く。
全損、高返戻にメス
生保各社が販売する一部の保険商品について、金融庁が業界への実態調査を始めたのは昨年6月のことだ。保険料の設定など法人向け定期保険の商品内容を問うアンケート票を送付したが、業界の返答は同庁が満足するものではなかったようで、その後も直接のヒアリングなどを含めて二度、三度と調査は続いた。
そして11月中旬、業界との意見交換の会合の場で、金融庁の担当者から10数社の幹部に対して直接、「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」との発言があった。要求の形を取ってはいるものの、これは監督官庁からの実質的な〝是正勧告〞に他ならない。
実態調査が始まってから、日本生命保険の清水博社長が7月に開かれた業界の会合で、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」と釈明するなど、節税効果を商品の売りにしているわけではないと強調してきたが、監督官庁の理解を得ることはできなかった。さらに一部報道によれば、金融庁は12月3日にも生保各社と会合を持ち、見直しについての姿勢を改めて問うたようだ。
今回、金融庁が問題視したのは、生保各社が販売する法人向けの全額損金の生命保険だ。2016年に日銀がマイナス金利を導入して以降、法人向けの主力商品であった各種の貯蓄型保険がそれまでのような高利回りを確保できなくなり、養老保険などの売り止めなどが相次いだ。
それに代わるように17年4月に日本生命から発売されたのが「傷害保障重点期間設定型長期定期保険」、通称「プラチナフェニックス」だ。支払った保険料は全額を会社の損金に算入でき、10年後に解約をすると支払った保険料の約85%が返戻金として戻ってくるもので、支払った保険料の額が会社の利益のまま残って法人税を課された場合よりも4割ほど多く手元に残るケースもあった。
この商品に経営者の加入が殺到したことから、各社も相次いで類似商品を発売した。東京海上日動あんしん生命「災害保障期間付定期保険」、アクサ生命「フォローアップライフ」、朝日生命「グランドステージ」など大手も競うように高返戻率を設定し、外資系生保では9割を超える返戻率をうたう保険商品もあり、顧客争奪戦はエスカレートしていった。
これらの保険は長い契約期間を設定しているものの、解約返戻金は加入後10年をピークとして急激に減少していく。商品の建前はどうあれ、加入者は最初から10年程度での中途解約を前提に契約を結ぶわけだ。この〝不自然〞な契約形態が金融庁の逆鱗に触れ、今回の強い是正要求につながったものと見られる。実態調査の過程で、オリックス生命が投入予定だった類似商品を販売延期とするなどの影響が出ていたが、今後も同様の動きや商品設計の見直しが実施される可能性が高い。
「付加保険料」を問題視

そもそも企業経営者にとって貯蓄性保険の強みとは、税金面でのメリットの大きさに加え、様々な面で会社にとって役立つことに他ならない。支払った保険料は損金算入され、払い込んだ保険料以上の金額が満期保険金あるいは解約返戻金として戻ってくる。解約すればまとまった額の現金がすぐ手元に用意できるためもしもの時の資金繰りにも使える。解約しなくても商品によっては積み立てた保険料の範囲内でお金を一時的に借りる契約者貸付を利用することも可能だ。法人契約をして満期保険金を退職金や役員の死亡弔慰金に充てることで財務の安定化にもつながる。
保険への加入は、もしもの時のための保障が最大の目的であることは言うまでもない。それに加えて自社の財務強化や老後の資産形成、または子の教育資金として大きく役立つことが、生命保険が会社経営に欠かせないとされるゆえんだ。
それでは経営者にとっての強い味方だった全額損金の法人保険は、今回の金融庁の是正要求によってどんな影響を受けるのか。保険各社が同保険に高い返戻金を設定できた理由は「付加保険料」にあると言われ、この部分が見直されるとの見方が強い。
付加保険料とは、販売や契約の維持のために生保会社が上乗せするコストの部分で、この部分は金融庁が新たな生保商品を認可する際のチェック項目に含まれていない。そのため各社は契約期間の後半の付加保険料を過度に厚くすることで、中途解約時に支払保険料のほぼ全額が戻ってくるアンバランスな設計を成り立たせていたカラクリがある。
金融庁はこの部分を特に問題視したといわれ、今後は付加保険料が見直されて返戻率の低下や保険料の値上げなどが行われるものと予想される。全額損金の法人保険という商品そのものが販売禁止となる可能性は低いと業界はみているが、同保険が人気を集めた理由である高返戻率のメリットが減るのはほぼ確実だといえるだろう。
もっとも〝お上〞の規制がこれで終わるとは限らない。過去には、全額損金をうたっていた「がん保険」について国税庁がアンケート調査を実施したのち、損金を全額から半額にするよう税制改正が行われたことがある。金融庁の実態調査の結果を受けて、後追いで生保を使った節税策を規制する税制改正や、国税庁による何らかの通達改正などが行われる可能性は否定できない。なお過去の事例などを見るに、すでに加入している既存契約については、さかのぼって税務処理などが見直されることはほぼないと思われるので、その点は安心だ。
掛け捨て保険も選択肢に
こうした変化を見据えたとき、今後は全額損金の定期保険のメリットが減ることを踏まえ、損益分岐点のシミュレーションなどの事前検討がより重要となるだろう。貯蓄型保険のなかから選ぶだけでなく、個人で加入している掛け捨て型保険を法人契約に掛け替えることも検討する必要があるかもしれない。
法人で契約した掛け捨て型の保険は、払い込んだ保険料の全額が損金となる。個人の保険を法人に掛け替えるだけで、会社としてまとまった額の利益圧縮ができるわけだ。もちろん貯蓄性がないからこその全額損金だが、掛け捨て型のなかには貯蓄型商品ほどではないものの一定の解約返戻金が見込める商品もあり、これらの保険についても、2分の1損金が認められているものがある。全損保険を見直すのなら、掛け捨て型も含めて商品を選びたい。
そして生命保険を契約する上での大前提として、保険本来の役割である「保障」についてもしっかり考えたいところだ。経営者にとって保険が果たす最大の役割は昔も今も変わらず、「もしもの時の保障」だ。自分に何かあった時の家族のためが第一。さらに中小企業では社長にもしものことがあれば会社はすぐさま機能不全に陥ってしまうため、会社の危機に備えることこそが保険に入る目的だ。
社長に何かあれば、家族は生活に困り、会社は立て直しを図るあいだにも銀行や仕入先への返済などが発生して「倒産」の二文字がちらつく。それらへの備えとしての役割が、生命保険の最大の価値であることは間違いない。
すでに契約している保険商品についても、定期的な見直しは必須だ。保険は一度加入すればおしまいではなく、経済情勢や会社の状況、社長個人のライフプランの変化に合わせて、細やかにメンテナンスを行ってこそ強みを最大限に発揮する。保険の見直しには様々な方法があるので、それらを把握して保障をフル活用したい。
生命保険には時代ごとのトレンドがあり、保険商品のラインナップも時期によって大きく異なる。しかし大前提として、経営者やその家族の求めるものを叶えられる商品こそが、自分にとっての最高の保険であることは言うまでもない。何を目的として保険に入るのか、そこをブレさせないことが社長には求められるだろう。
(2019/02/04更新)
